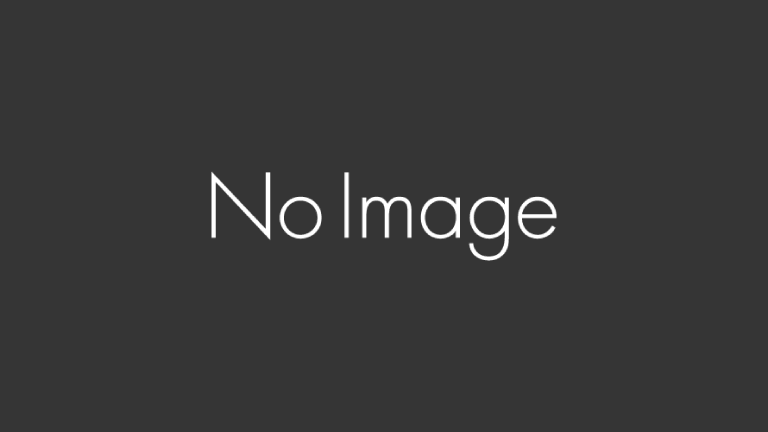皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。
今回は【働き方と健康格差】シリーズ第二弾です!
シリーズ①は主に「健康格差が生じる要因」について、シリーズ②は主に「職域における対策」についてまとめています。
参考文献は引き続き、『健康格差社会への処方箋』(著:近藤克則、出版:医学書院)です。
膨大な研究内容がコンパクトにまとまっていて、初めて社会医学を学ぶという方にもオススメの一冊です!
もし皆さんが、今現在のご自身の働き方に悩んでいるのだとしたら、その働き方を続ければ健康を害してしまう可能性が高いです。
今回の記事を読んで、その働き方を改善することが出来るのでしたら、そんな由々しき未来を回避することが出来るかもしれません。
今回の記事が、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
是非ご一読ください!
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。皆さんは、ご自身が「健康的な働き方をしている」と思いますか?一般的な臨床医は、下記のような働き方をしています。皆さんの中にも、当てはまる方がいるのではないでしょうか。慢性的な長時[…]
メゾレベルの3つの特徴
本書では、対策・政策の介入対象を下記3つのレベルに分けて考えています。
- ミクロ(個人、家庭)
- メゾ(職場、学校、コミュニティ)
- マクロ(国、社会)
この内、メゾレベルの「職場」におけるリスクだけを抜き出しても、下記の様に様々なものが挙げられます。
- 正規雇用者:長時間労働、サービス残業への対策、ワーク・ライフバランス
- 非正規雇用者:派遣・請負・パート労働者、ワーキングプア、フリーター等への対策
- 両者共通:職場でのメタボリック・シンドローム対策、職業性ストレス対策、メンタルヘルス対策(うつ・過労死・自殺等)
しかし、メゾレベルの取り組みには下記3つの様な特徴があり、判断を難しくさせています。
- ミクロとマクロの両面からの影響を大きく受けている
- 1人の人が多くのコミュニティに属している
- メゾレベルだけにおける効果の検証が困難
一つ一つ、詳しく説明していきましょう。
ミクロとマクロの両面からの影響を大きく受けている
メゾレベル(例えば職場における健康問題)は、ミクロレベル(例えば個人の生活習慣や家庭での介護問題等)の影響も受けています。
ある職場やコミュニティに属する人たちの健康状態が悪かったとしても、
そのうちのどの程度が個人の要因に起因している(例えば、健康に良くない生活スタイルを取っている個人がそこに集まっているせい)か、
それとも職場やコミュニティのあり方に起因している(例えば、健康的な生活スタイルだった人でも、そこに移ってきてから不健康になった)かを、厳密に区別するのは容易ではありません。
また、対策を考える時、国による法律・規制・予算等の多面的な政策的支援なしに、職場独自の対策だけで進める対策は、十分な効果を期待出来ないことも多いです。
この特徴のため、メゾレベルへの対策であっても、ミクロやマクロレベルからのアプローチを含む、総合的な対策を必要としています。
1人の人が多くのコミュニティに属している
ほとんどの人々は、複数のコミュニティに属しています。
考えられるのは家庭、職場、地域、趣味、子ども繋がり等のコミュニティですが、
本書では、SNSも一つのコミュニティとしてカウントしています。
確かに、オンラインコミュニティやオンラインゲーム等、オンライン上で人間関係を築くのが当たり前の時代です。
職場だけの取り組みでは十分ではなく、他との連携した取り組みが必要とのことです。
メゾレベルだけにおける効果の検証が困難
介入研究で効果を検証する時にも、ミクロ(臨床)レベルのように、無作為化対象比較試験をすることは出来ません。
その一方で、先駆的な試みが、WHOやILOのような国際機関から草の根レベルまでの広い範囲でみられます。
その理由は、上述の2つの特徴があるにも関わらず、職場やコミュニティ等のあり方が健康に影響していることは経験的に明らかだからでしょう。
色々な取り組みによって、どのような、どの程度の効果があるのか。
科学的・実証的な評価研究に加え、新聞報道レベルのものも含めた様々な手立てがあり得ることを示していきます。
職場でのリスクと取り組み①メタボリック・シンドローム
働き盛りの世代の多くは職場で多くの時間を過ごしており、そこで多くのリスクにさらされています。
それらのリスクへの対策も、職場や事業所・企業レベルで出来ることが色々あります。
健康的な食事の提供
家森が、ヘルシーランチメニューという取り組みを紹介しています(日本経済新聞2006年7月2日)。
40~63歳の53人の対象を、栄養バランスに配慮した「ヘルシーランチ」群と、大豆や魚を多用した(イソフラボンやDHA)「強化ランチ」群の2群に分けた二重盲検です。
1ヶ月間で、両群とも肥満度や血圧が改善したほか、「強化ランチ」群では悪玉コレステロールが減少し、善玉コレステロールは増加し、動脈硬化のリスクが1割下がったといいます。
健康経営
メタボリック・シンドロームをはじめとする生活習慣病やメンタルヘルス等、従業員の健康に配慮した経営を行う「健康経営」(NPO法人健康経営研究会の登録商標)が注目されています。
経済産業省によれば、「健康経営」とは、「従業員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるという考えの下、従業員の健康管理を経営的な視点から考えて、戦略的に取り組むこと」です。
従業員の健康が良くなることで、健康保険組合の保険料の抑制になるだけでなく、体調不良による早退・欠勤の減少、生産性の向上等、経営活動にも良い効果がみられるとする『会社の業績は社員の健康状態で9割決まる』と題する書籍も出ています。
経済産業省は「企業が従業員の健康づくりを経営的な視点で捉え、戦略的に取り組むことは、従業員や組織の活性化をもたらし、結果的に企業の業績向上や株価向上に繋がる」ことまで期待しています。
個人の生活習慣が原因とみなされがちなメタボリック・シンドロームの原因は、実は職場にもあります。
職業性ストレスが高い状態にさらされている人では、他の生活習慣等の影響を差し引いても、およそ2.25倍もメタボリック・シンドロームが多かったという報告があります。
となると、対策も職場レベルで必要になります。
職場ぐるみで取り組めば、個人による努力だけより大きな効果が期待出来ます。
ただし、気を付けなければならないのは、対象となる社員は誰かという点です。
ある企業では、割安で健康的なメニューがある社員食堂を使えるのは正社員のみで、社員証を持たない非正規雇用の社員は利用出来ないといいます。
社員食堂を使え、健康経営の対象とされ、メンタルヘルスチェックの対象とされるのが正社員のみというやり方では、正規・非正規労働者間の健康格差を助長してしまいます。
職場でのリスクと取り組み②長時間労働
先進国でも飛び抜けた長時間労働
日本では異常な長時間労働がみられることは、シリーズ①「健康格差が生じる要因」でも述べました。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。皆さんは、ご自身が「健康的な働き方をしている」と思いますか?一般的な臨床医は、下記のような働き方をしています。皆さんの中にも、当てはまる方がいるのではないでしょうか。慢性的な長時[…]
日本では、会社員5268万人のうち、10人に1人以上(617万人)が、夜10時過ぎまで残業していました。
「先進国で飛び抜けた『(残業)大国』」です(朝日新聞2007年2月8日)。
ILOの国際比較データ(2005年)によると、週に50時間以上労働している就業者の比率は、ヨーロッパの12ヶ国では10%前後です。
イギリスが約12%、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド等が15%前後で、いわゆるアングロサクソン系と言われる国々で多いです。
それらに対し日本は28.1%と、正に「飛び抜けている」のです。
長時間労働は、一般には職階が低い層に多くみられ、健康を壊す原因になるので、職場における健康格差の原因となります。
ではどうしたらよいのでしょうか。他国の長時間労働抑制策を参考に見てみましょう。
残業代の割増率の引き上げ
まずは残業代の割増率の引き上げです。
平日の割増率は、日本では基本賃金の25%以上となっていますが、アメリカでは50%です。
日本の休日割増率は35%ですが、ベルギーのように100%という国も複数あります。
総労働時間の規制
残業代の割増率を引き上げただけでは問題は解決しません。その理由は2つあります。
1つは、サービス残業(不払い残業)の存在です。
労働者の2人に1人が経験しており、1社100万円以上のものに限っても、厚労省が摘発した総額は2005年で233億円にも上りました。
医師の時間外労働などに対する割増賃金に未払いがあったとして、宮城県気仙沼市の気仙沼市立病院が未払い分として対象者79人に…
もう1つは、合法的な残業です。例えば、医師の長時間労働の一因である「当直」は、現在の労働基準法では労働時間とみなされません。
これらの「穴」を塞いでからでなければ、割増率を引き上げても問題は解決しません。総労働時間の実効性のある規制が必要です。
【補足】
本書は2016年12月に発行されました。
その後、2019年4月から大企業で、2020年4月から中小企業で「働き方改革」がスタートしました。
医師については5年間の猶予期間が設けられ、いよいよ2024年4月から「医師の働き方改革」がスタートします。
そこでも「宿直」の扱いについて明記がされています。過去記事にまとめてありますので、是非チェックしてくださいね!
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。「医師のより良い働き方を考える」当ブログが決して無視出来ない案件がひとつ…そう、「医師の働き方改革」です。2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が適用されるんだ[…]
仮に規制が強化されても、日本では「無言の圧力」により実質的な残業が減らず隠れ残業となる恐れもあるので、職場の空気(規範)を変える必要があります。
ノー残業デイの実施や強制的な一次消灯等で残業を減らそうという、企業・事業所レベルの取り組みも行われています。
職場でのリスクと取り組み③職業性ストレス
職場内での社会サポート・ネットワークの再構築
仕事上要求される負荷量が多くても、同僚のサポートがあれば、ストレスを緩和出来ます。
しかし、成果主義の導入で、成果として評価されない同僚や部下へのサポートは弱くなり、社員同士の繋がりも希薄化しました。
そのことがストレスを高めているという声は多かったとのこと。
企業側の危機感もあって、社員同士で表彰する機会を設けたり、親睦会や運動会、社員旅行等を復活させたりする動きが広がっています。
これは職場における社会サポート・ネットワークの再構築によって、職業性ストレスを緩和する試みといえます。
ヨーロッパにみる体系的な対策
この面でもヨーロッパに先駆例があります。
職場ストレス対策の進み具合を、6つの基準(法律的枠組みがあるか、国レベルでのモニタリングシステムはあるか、ストレス対策は組織志向か個人志向か両方か、ストレスのコストと対策のベネフィットに関する信頼するデータはあるか等)で、11ヶ国を3つのグループに分けた報告があります。
それによれば、北欧が先頭集団です。
これらの国では、労働環境法(スウェーデン、1991年)等の法的な整備がなされ、経営トップや管理職を巻き込んだストレス対策プログラムが導入されると共に、その効果評価がなされています。
その中から、ストレス対策費用を上回る生産性の向上と、ストレス関連障害の減少という効果を報告した例もみられるとのことです。
日本でも、精神障害を原因とする労災認定件数の増加等を受け、
労働者の安全と健康の確保対策を充実させるため、2014年に労働安全衛生法が改正されました。
労働者の心理的なストレスの程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施も2015年12月から事業者に義務付けられました。
事業者は労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、必要な場合には、作業の転換・労働時間の短縮等適切な措置を講じなければならないこととなりました。
職業性ストレスは職階が低い層で高い傾向があるので、それを緩和することで、健康格差を抑制出来る可能性があります。
ただし当分の間、従業員50人未満の事業場については努力義務とされており、中小企業と大企業の間の格差は広がる恐れがあります。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。臨床医の皆さんは、永遠に押し寄せる患者の波に疲弊したことはありませんか?私は臨床医時代、次のような悩みを持っていました。「私が毎日、外来に溢れる患者を[…]
安全性と競争力は競合するのか
企業の立場に立ってみれば、激しくなる国際競争で勝ち抜くためには、生産性を高め、競争力をつけることが必要です。
その手っ取り早い方法が、人を雇わない(あるいは人員削減)で、少ない労働者にサービス残業や長時間労働をさせること、成果主義賃金を導入して総人件費を抑えることです。
だから「これらを規制することは現実的でない」という経営者の声が聞こえてきそうです。
確かにこれらは確実に効率を高める方法です。ただし、短期的に見れば、です。
無理は長続きしない。過酷な労働環境は、早期離職を招き、残った人材には更に負担がかかり、人材は育たないのです。
実際、競争力と労働災害による死亡事故との関係を見てみると、安全性と競争力との間に負の関係が見出せます。
健康な職場や国の方が、大局的、長期的に見れば、生産性や競争力は高いのです。
部分的、短期的に見れば、どのような国、どのような企業であろうと、
競争相手が同時に同じような行動をとらない限り、労働者に望ましい施策を導入する余裕はありません。
だから企業任せでは上手くいかないのです。
適切な規制(ルール)づくりや制度設計等、国でなければ出来ないことがあります。
当たり前のことを企業や国にさせるのには、「世論の力」や社会対話(social dialogue)が必要です。
安全で健康な職場
社会対話を推進することも使命とするILOが提唱しているのが、「安全で健康な職場」の取り組みです。
その基本文書の中では、まず国際的な労働に関する基準と基本原則、仕事に関わる権利の重要性を述べています。
そして貧困から脱出出来る賃金水準等を中心的要素とするディーセントな(働きがいのある人間らしい)雇用(decent employment)を保障することが、
安全性や健康水準だけでなく生産性も高めると指摘しています。
そして、「全ての人に社会的保護を(Social protection for all)」提供するために、事業者と国の両方におけるマネジメントシステムの導入や教育・訓練・情報の提供等を行うべきと述べています。
これらの取り組みを進めるためには、雇用者と労働者と政府の3者間、および社会対話が重要としています。
また、ILO憲章が謳う様に「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」。
つまり、国際的な協調による労働者を守るための「もう1つのグローバリゼーション」が必要です。
まとめ
職場での具体的なリスクと取り組みとして、下記3つを取り上げました。
- メタボリック・シンドローム
- 長時間労働
- 職業性ストレス
皆さんが今現在、上記のいずれかに悩まされているのだとしたら、
今回の記事で紹介したメゾレベルの対策を実践することで、事態が改善するかもしれません。
しかし、国や医療機関が動かない限り、メゾレベルの取り組みを推し進めることは出来ません。
もしも皆さんの職場が、皆さんの労働環境を改善する見込みが無いのだとしたら…もしくは、見込みはあるがそれを待てないのだとしたら、
シリーズ①でも述べたように、個人でも出来る対策として「転職」をオススメします。
皆さんがより良い働き方が出来る職場がきっとあるはずです。
皆さんが心身共に健康的に働けるようになることを、心よりお祈り申し上げます。
『更紗の医師転職ブログ』にようこそ。こんにちは、管理人の更紗(さらさ)と申します。このブログでは、働き方に悩む臨床医を対象に、より良い働き方を考えるのに役立つ情報を提供しています。何故、わざわざそんなことをしているの[…]