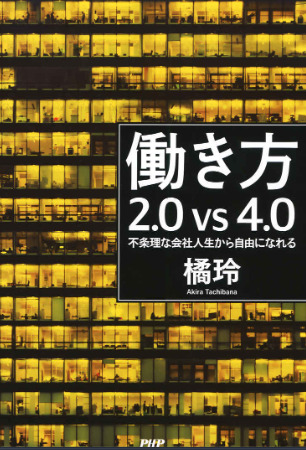気付いていますか?web3時代の到来
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。
「世界は、新しいルールで動きはじめた」
これは伊藤穰一さんが、著書『テクノロジーが予測する未来〜web3、メタバース、NFTで世界はこうなる』(発行:SB新書)で一番最初に書いていらっしゃった文章です。
伊藤穰一さんは、これまでに米マサチューセッツ工科大学メディアラボの所長を務めたり、ニューヨーク・タイムズ社やソニー株式会社の取締役を歴任されてきた、
「社会とテクノロジーの変革」に取り組んでいらっしゃる、web3(ウェブスリー)分野の第一人者です。
この書籍には、web3のことが広く深く分かりやすく、リテラシーに配慮して書かれており、うなるほど素晴らしかったです。
これからweb3を学び始めるのでしたら、「一番最初にこの書籍を読むべき」と断言できます。
今回の記事では、伊藤穰一さんの書籍を参考に、web3時代の新しい働き方について予測していきます。
今後の働き方を模索している方は必見です!
是非ご一読ください。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。2023年も爆速で過ぎ去ろうとしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の記事は、毎年恒例の「今年の振り返り&翌年の抱負」に加え、翌年の抱負に絡んでくるのですが、生成AI[…]
ウェブの歴史をさかのぼろう Web1.0とWeb2.0の時代
まず、「ウェブは知ってるけど、3って何?」と疑問に思われる方が多いと思います。
これは、端的に言うとこれまでのウェブの歴史を3つに区切り、バージョン設定したものです。
なので、書籍内ではWeb1.0、Web2.0という言葉も頻出します。
(伊藤さんがWeb3.0ではなくweb3という表記にしているのは、web3の「分散性=非中央集権的」という性質を表すためだそうです。)
ここで分かりやすいよう、私なりに下記のような表にまとめてみました。
| ウェブの変遷 | 代表する媒体・技術 |
| インターネット0(ウェブは存在しない) | eメール |
| Web1.0 | ホームページ |
| Web2.0 | SNS |
| web3 | ブロックチェーン |
ひとつひとつ見ていきましょう。
インターネット0
インターネット0とは、eメールでつながっていた時代。当時「ウェブ」と呼べるものは存在していませんでした。
しかし、このことで、電話会社がひっくり返されることになったのです。
当時日本の通信事業は、事実上、NTTによる独占状態でした。
しかし「NTTのダークファイバー(未使用回線)の開放」や「接続料のアンバンドル化(パソコン・インターネット・回線接続会社などを別々の事業者に分割すること)」などの施策がとられたことで、他社もインターネット事業に参入できるようになりました。
Web1.0
一方、Web1.0とは、ホームページが作られるようになった時代です。ウェブ黎明期ともいえます。
新聞社・出版社・放送局の力を借りなくても、世界中にダイレクトに情報を発信することができるようになり、
同時に多くの人々をウェブに呼び込むことで、ウェブのビジネスモデルとして広告が定着することになりました。
これにより、今度はメディア、広告業界がひっくり返されることになりました。
eコマース(インターネットを使って売買をすること)の普及もWeb1.0の特徴的な現象です。
Web2.0
Web2.0は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が普及した時代です。
一部の誰かが情報を発信し、多くの人はそれを閲覧するだけだった一方向性(発信者→受信者)のWeb1.0とは異なり、
Web2.0では多くの人が自ら発信し、他者の発信を閲覧する双方向性(誰もが発信者であり受信者)が認められます。
これにより、ポータルサイトがひっくり返されました。
ポータルサイト(例:Yahoo!)とは、1つのサイト内にさまざまなコンテンツの「入り口」を設け、ユーザーはまずこのポータルを訪れてから、自分が求める各コンテンツに飛ぶというものです。
検索エンジン(例:Google)もこの一種で、Web1.0ではポータルサイトが流行しました。
しかしWeb2.0では、次第にこれらの力が弱まっていきました。
時代の中心はどこだ?
Web1.0時代、そこに中心はなく、分散的なサーバーが世界中に点在していました。つまり非中央集権的な構造でした。
ところがWeb2.0になると、SNSのプラットフォームを提供している企業の力が大きくなりました。数少ない企業が中心に展開する、中央集権的な構造になってきたのです。
※G:Google A:Amazon F:Facebook(現:Meta) A:Apple M:Microsoft
とはいえ、「1つの場にユーザーを囲い込んでいる」という構図は、Web1.0のポータルサイトもWeb2.0のソーシャルメディアも変わりません。
そこに劇的な変化が起ころうとしているのが、web3なのです。
ブロックチェーン技術で可能になったもの
web3がWeb1.0、Web2.0と決定的に違っている点は、ひとことでいえば「分散的=非中央集権的」ということにつきます。
それを可能にしたのは、web3の重要なインフラである「ブロックチェーン」という新しい技術です。
ブロックチェーンとは、簡単にいうと「暗号技術を使って決済(支払い)などの取引(トランザクション)履歴を1本の鎖のようにつなげて記録する(その記録は誰もが閲覧可能)」技術です。
この技術により、下記のようなことが次々に可能になったのです。
- 仮想通貨/暗号資産
- DeFi(Decentralized Finance, 分散型金融)
- NFT(Non-Fungible Token, 非代替性トークン)
- メタバース
- DAO(Decentralized Autonomous Organization, 分散型自律組織)
仮想通貨/暗号資産 ビットコインとイーサリアム
「仮想通貨といえばビットコイン」というイメージを持っている方も多いと思います。
2009年1月、サトシ・ナカモトという謎の人物によって、ブロックチェーンの理論が提唱されました。
その後、ブロックチェーン技術を応用し、世界で初めて開発された仮想通貨/暗号資産が、「ビットコイン」です。
その背景には国家の統制を逃れようとするリバタリアン的な発想があります。

一方、2015年には「イーサリアム」という仮想通貨/暗号資産も開発されました。
これはビットコインとは別の意味で画期的といえるのです。
イーサリアムもビットコインも、ブロックチェーンを用いた仮想通貨のプログラムですが、両者にはまったく異なる思想的背景があります。
ビットコインは、トラストレスで非中央集権的であるために、いままでは主に「通貨」としてしか機能していません。
イーサリアムと比べて、プログラム言語を使って運用・管理しにくいために、開発が難しかったのです。
一方、イーサリアムは、ビットコインのような通貨としての機能にみずからを閉じ込めませんでした。
「スマートコントラクト」(あらかじめ取り決めた処理を自動的に実行し、ブロックチェーンに記録するデジタルな契約書のようなもの)などの仕組みを備えることで、イーサリアムはさまざまなアプリケーションの開発ができるようにしたのです。
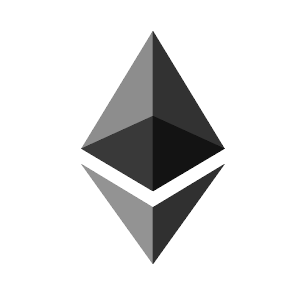
簡単にいうと、ビットコインは通貨、イーサリアムは通貨であると同時にインフラ(基盤)でもある、ということです。
DeFi、NFT、DAO…、web3を構成する要素は、すべてイーサリアムというインフラ上で可能になったものです。
イーサリアムは、コミュニティベースで成立する経済圏を生成し、「分散」をキーワードとするweb3の多様な経済・社会活動を可能にしているのです。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。皆さんは、医師になって何年が経過しましたか?「医師になってから今まで、ずっと総合病院で同じように働いている」…そんな方も多いと思います。しかし世界では、特にアメリカでは、人々の働[…]
2つの経済圏 フィアットエコノミーとクリプトエコノミー
経済圏についても説明していきます。
法定通貨の世界、これを「フィアットエコノミー」と呼びますが、
web3では、「クリプトエコノミー」という新しい経済圏が形成されています。
この経済圏では、円やドルといった法定通貨(フィアット)ではない暗号資産(クリプト=仮想通貨やトークン)が流通しています。
フィアットエコノミーでは、経済や政治は国による管理とトップダウンの決定、企業などの組織運営は経営者による管理とトップダウンの決定と、あらゆることが中央集権的です。
一方、多くのプロジェクトが中央集権的な管理者の存在なしに、個人や組織、資産が分散的・自律的に動き回っている経済圏が、クリプトエコノミーなのです。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。もっと強くなりたい…力がほしい…「稼ぐ力」が…!(少年マンガ風)私は常々そう思っているのですが、皆さんはいかがでしょうか?「稼ぐ力」は、実は「働いても働かなくてもいい」という経済[…]
Web1.0は「読む」、Web2.0は「書く」、web3は「参加する」
「コミュニティありき」という視点を踏まえて、ここで改めてWeb1.0、Web2.0、web3の変遷について考えてみましょう。
端的に言えば、Web1.0ではグローバルに「read=読む」ことが可能になり、
Web2.0ではグローバルに「write=書く」ことが可能になり、
そしてweb3ではグローバルに「join=参加する」ことが可能になりました。
一般的にはweb3は「own=所有する」という言葉がよく使われていますが、伊藤さんはあえて「join=参加する」と表現したいと仰っています。
つまりWeb1.0、Web2.0、web3という流れのなかで、できることが「変化した」のではなく、「増えた」ということです。
【DAO】web3時代の新組織
web3では、個人の働き方は「組織ベース」ではなく「プロジェクトベース」になっていきます。
その主体はDAO(ダオ)です。
DAOは会社組織ではなく、プロジェクトごとに立ち上げられるので、
個人は自分が興味を持ち、貢献できそうなDAOを見つけるごとに「参加する」というかたちで働いていくことになります。
さまざまな機能を包摂する企業組織とは違って、DAOは1つの目的、1つの機能に特化したものです。
プロジェクト運営を目的とするDAOもあれば、プロジェクト運営に必要なインフラやアプリケーションを開発するDAOもあります。
そこでDAOは、必要に応じてさまざまなアプリケーションを組み合わせ、プロジェクトを運営していきます。
いわば「D to D(DAO to DAO)ビジネス」があることで、プロジェクトDAOは、すべての機能を包摂することなく、必要に応じてほかのDAOと結びつきながら、みずからの目的を純粋に追求していくことができるわけです。
「経営」「組織運営」というものについて回る数々の面倒や困難が軽減されており、「面倒で難しいことを担う経営陣」「その経営者の下で仕事をする従業員」というヒエラルキーが存在しません。
そして手軽で簡単であるというのは、成長速度が上がりやすいということでもあります。
【DAO】勤め先に縛られなくなる
まだロールモデルがいない新しい働き方が、DAOというコミュニティから生まれてくる。
「こんな働き方があったんだな」という、働き方のイノベーションが、web3のなかで多々起こっていくと思います。
プロジェクトを実際に動かしていくにはさまざまな役割が必要であり、それは、何もエンジニア等の専門職とは限りません。
「自分には手に職がないから無理」「腕一本でやっていける人しか働けないのがDAOだ」などと思ったかもしれませんが、本当は誰もがDAOに参加し、貢献できる「何か」を持っているはずなのです。
自分から「これ、やります」と手を挙げられるようになっているので、嫌いなことや苦手なことを割り振られることはありません。
タスク単位で働いてトークンを受け取ることもできますし、場合によっては、もっと深くコミットするミドル~コアコントリビューターとして、定額のトークンを給料のように受け取る場合もあります。
DAOでは、このように多様な働き方が可能であり、自分が望むかたちで、自分が望む時間だけ参加できる。
これは、働く主体としての自分を、組織から自分の元へと取り戻すことを意味するといっていいでしょう。
自分の仕事や働き方は、組織に決められるのではなく、自分で決めるということです。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。皆さんも、「石の上にも3年」(意味:辛いことがあっても3年間は耐えるように)という言葉をご存知だと思います。実は私も、今の会社に「最低でも5年間は勤めよう」と決意して入職しました。[…]
【DAO】法整備はこれから
いってみれば、すでに既存の国家による法の支配を超えたところで機能してしまっているのがDAOであり、それがweb3の常識になっている。
今後はさまざまなかたちでフィアットエコノミー側も影響を受けていくと思われるので、無視できなくなるはずです。
現時点でもっとも先進的な例としては、アメリカ・ワイオミング州でDAOを法人として認める「DAO法」が制定されました。
一方、日本ではようやく議論がはじまろうか、というくらいの段階です。
このあたりの法整備が進めば、DAOによる仕事や働き方の劇的な変化は、より大きな社会的ムーブメントになっていくでしょう。
【DAO】格差是正につながるか
仕事の内容も場所も時間も、誰かに指示されるのではなく、自分主導で決められるというのが、web3的な働き方です。
そういう働き方が当たり前になれば、仕事にまつわる格差を小さくしていくこともできるでしょう。
たとえば男女の格差。日本のジェンダーギャップ指数は156ヵ国中120位前後と、惨憺たる状況が続いています。
男性優位の価値観はもちろん正していかねばなりませんが、仕組み面でボトルネックとなっているのは、やはり妊娠・出産という大きなライフイベントに対する無理解や不寛容でしょう。
男性の育休など、以前に比べれば改善している部分もあるのかもしれませんが、まだまだ、子どもを持つ女性が働きづらいという現状があります。
こうした男女格差以外にも、介護などさまざまな事情によりフルタイムで働けない人、あるいは自身の心身が不自由で、会社に出勤することが難しい人もいるでしょう。
既存の社会では、どうしても、そういう人たちが置き去りにされがちでした。
しかし、「自分にできること(得意なこと、好きなこと)で貢献できればOK」「いつ、どこで、どれだけ働いてもOK」というDAOならば、さまざまな事情で既存社会の固定された働き方が難しい人たちにも、多様な働き方の可能性が開かれます。
いままで、フィアットエコノミーではやりたいことを見つけられずにいた人や、やりたいことがあっても具現化する手段のなかった人が、クリプトエコノミーで開花することもあるでしょう。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。当ブログの読者の皆さんの中には、女性の方もいらっしゃると思います。「医師は男女問わず活躍できる職業」とはいえ、まだまだ長時間労働・当直・日直が当たり前の男性優位社会です。働いてい[…]
まとめ
私たちが、web3時代を避けることは出来ません。
社会のあらゆるレイヤーで非中央集権化が起こるweb3では、個々が己の価値観や趣味嗜好、ライフスタイルに従い、思い思いのかたちで社会参加するようになることでしょう。
新時代の到来に、私はとてもワクワクしています!
皆さんも、是非一緒に考え、参加していきましょう。
※今回、新カテゴリ「テクノロジー」を作りました。今後もweb3やAIについて記事にしていくつもりなので、また遊びに来てくださいね。