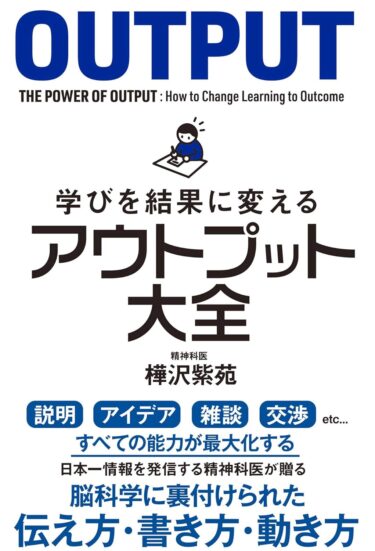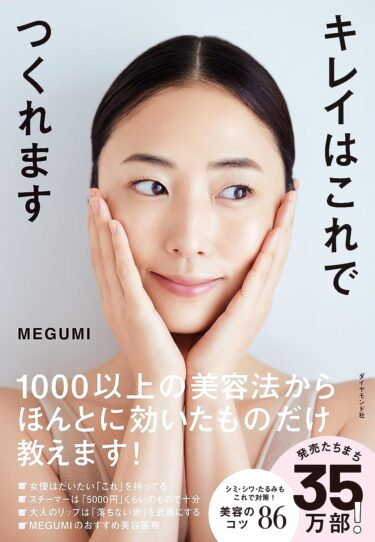「余白のある暮らし」のススメ
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。
皆さんの生活には「余白」、ありますか?
私は最近、体調を崩したことをきっかけに「余白のある暮らし」を心がけるようになりました。
「余裕のある暮らし」とか「ゆとりのある暮らし」という言葉ならよく使われていると思いますが、それだと充実感・満足感がないといけないような印象を受けるかなと思いまして…
本当に何もせずぼーっとして、とくに充実感・満足感は感じていない…それでもOK!という意味を込めて、私は敢えて「余白のある暮らし」という言葉を使っています。
今回の日記では、「余白のある暮らし」を意識することになった経緯について、また「私が実践中の余白のある暮らし」について、つらつらと書いています。
多忙な皆さんにも、どこか共感していただけましたら嬉しいです!
ずっと「余白がない」スケジュールで暮らしてきた
「子どもを医者にしたい!」という両親の期待を背負っていた私は、「勉強をしない時間」にとてつもない罪悪感を抱く子どもでした。
手持ちの問題集を全て解き終わってしまい、「空いた時間に何をしたらいいのか分からない」と泣くほどでした(苦笑)。
眠る時間にすら罪悪感を抱いていたので、小学生〜高校生の時の睡眠時間は3時間程度でしたね。
慢性的な睡眠不足で、全然効率的に勉強できていなかったのですが、子どもの時にはそれが分かりませんでした。
周囲の大人は「もっともっと勉強しなさい!」ということは言っても、「休むこと」については教えてくれませんでしたからね。
私は「医師になったらこの苦しみから解放されるはず」と思って耐え抜いたのですが、
なんと、医師になったら更に眠れないし勉強しなければなりませんでした(笑)。
(笑いどころじゃない)
臨床医から産業医に転職して、もう4年半ほどが経過しました。
子どもたちの夜泣きもなくなり、今は睡眠時間は7時間程度は確保できるようになりました。
それなのに、最近、動悸が止まらないことが一週間ほど続きました。
自分が医師なので「これはちょっと普通じゃないな」ということにはすぐ気付き、
何でこうなったんだろう?と考えてみたところ、自分の生活スタイルに原因があるようでした。
仕事の休み時間も、ずっと仕事をしていたり急いで読書をしていたり。
通勤中の車の中でも、急いで耳学習したり英語のシャドーイングをしたり。
家でも、家事・育児を終えたわずかな自由時間は急いでブログを書いたり。
普段まとまった自由時間というものがとれないので、やりたいことをやるにはスキマ時間を活用するしかないのですが、
そのために、ほとんど「余白がない」スケジュールで生活を送っていたのです。
日本人は休むのが苦手!?
日本人が「休む」ことをしていない、もしくはできないことを象徴するようなデータが実はたくさんあります。
- 有給休暇の取得率が低い(政府目標は取得率70%だが、未だ56.3%)
- コロナ禍前は有給休暇取得率が世界で連続して最下位だった
- 余暇や睡眠を含めた自分のケアのための時間が、日本は調査対象国の中で最下位だった
この内容は『健康になる技術大全』(著:林 英恵、発行:ダイヤモンド社)に書かれていたものです。
この本は、世界最先端のエビデンスに基づいて書かれた「健康習慣」の本です。
「健康になるためには、この本を読んでその内容を実践しておけば間違いない」と言っても過言ではありません。
今現在ご自身の健康を犠牲にして働いていらっしゃるだろう臨床医の皆さん(決めつけてすみません…)には、是非お読みいただきたいです!
著者の林先生は、ハーバード大学の公衆衛生大学院の社会・行動科学部で、日本人女性として初めて、パブリックヘルスの博士号をとられた方です。すごいですね…!
そんな林先生自身も、「休むことが苦手」だったと、この本の中で書かれています。
たった1日休んでも、罪悪感や焦燥感、不安感に苛まれてしまう、ワーカホリック(仕事中毒)な自分を発見することとなりました。
それから、ヨガや瞑想を始め、今までだったら、「時間の無駄」と思って取り組んでこなかったようなことに、取り組んでみようと思い始めました。
私も林先生に共感できました。
やっぱり日本人は、「意識して休む」くらいがちょうどいいようです。
意識して「余白」を設けよう
ここからは、私が最近実践している「余白を作る方法」を一部紹介させていただきます。
あくまで私のやり方ですが、参考になりましたら嬉しいです。
実践にあたり、私が参考にした書籍は、先述の『健康になる技術大全』と、
当ブログおなじみ『アウトプット大全』(著:樺沢 紫苑、発行:sanctuary books)です。
ご興味ある方は、是非読んでみてくださいね。
「空間の余白」を作る方法
- 物を徹底的に減らす
- 物が視界に入らないようにする
まずは休むことができる環境を整えるために、「空間の余白」を作ってみましょう。
物を徹底的に減らす
視界に入る物の量が多い=情報量が多いため、思考を休めることができません。
まずは物を徹底的に減らしましょう。
ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアン教授の研究によると、人間は1日に最大で3万5,000回の決断を下しているそうです。
当然ながら、決断する回数が多いほど脳は消耗し、「決断疲れ」を引き起こします。
例えば、服の枚数が多いと「今日どの服を着よう…」と悩みますよね。
しかし、服が2着しかないのであれば交互に着ればいいので、もう悩むこともなくなります。
物を減らすことは、決断の回数を減らして脳を休めることに繋がるのです。
私は断捨離大好きで、元々物が少ない方です。いつか断捨離についての記事も書こうと思います!
物が視界に入らないようにする
物を減らした後は、物が散らかっている=思考が散らかっていることになるため、
物をまとめて視界に入らないようにするのがオススメです。
例えば、子どものおもちゃがリビング中に広がっているのが見えていたら「早く片付けないと」とイライラしてしまいますが、
ベビーサークルの中でだけおもちゃが散らかっているのだったら「後でゆっくり片付けるか…」と一呼吸置くことができます。
休みたい時は、視界に何も物が入らないように。それが難しい時は、目を閉じるのでもいいですね。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。皆さんは「今の職場で、今の仕事を、一生続けたい」と思いますか?働き方に悩んでいるくらいですから、答えは当然「NO!」だと思います。不満があっても、「専[…]
「時間の余白」を作る方法
- ゆとりあるスケジュールを組む
- 「休養するための時間」を先取りする
放っておくとすぐに一日のスケジュールがパンパンになってしまいますよね…。
私もそうで、大学院生時代はバイトでパンパンで一日も休みがありませんでした(笑)。
ですが、ちょっとの工夫で、余裕を持ったスケジュール管理が可能になります。
ゆとりあるスケジュールを組む
仕事の話になりますが、私は産業医面談は1件あたり1時間と見込んでスケジュールを押さえます。
面談自体は15分〜30分程度で終了し、面談記録作成・書類作成など込みで考えても1時間も必要ありません。
しかし、面談後の小休憩を確保するために、1時間でスケジュールを組んでいるのです。
私にとって産業医面談はかなり集中力を要する業務で、1件やるだけでも疲労を感じてしまうからです。
空いた時間は何をしても自由ですが、なるべくトイレに行ったり、お茶を飲んだりして気持ちを切り替えます。
それだけでも、立て続けに面談をするのと比べ、次の面談への集中力が高まるのが分かります。
「休養するための時間」を先取りする
『アウトプット大全』の中で、著者の樺沢先生は、”「脳科学的」理想の1日の過ごし方”を教えてくださっています。
「8時〜9時 朝活時間:会社近くのカフェで極上のアウトプット時間」
「9時〜12時 脳のゴールデンタイム:この時間帯に集中力が必要な仕事を終わらせる」
などが書かれており、一日中バリバリ活動しているのかと思いきや、
意外にも午後は「休養するための時間」を多く設けているのです。
- 14時〜15時 ゆるい時間:食後の眠気も出て集中力が下がる。ゆるい作業、打ち合わせなどで乗り切る
- 19時〜21時 クリエイティブ時間:夕食を兼ねて友人、家族とのコミュニケーション。また娯楽や運動で明日への活力を養う
- 21時〜22時半 リラックス時間:寝る前2時間はのんびりと過ごす
- 23時〜6時 睡眠時間:7時間以上を確保
脳科学的にも最適解のこのスケジュールを組むためにも、「休養するための時間」を先取りしておくべきです。
私は寝る直前まで猛烈に作業していて(子どもの幼稚園の準備とかワクチンの準備とかブログとかで…)、
いつも「あっ、もうこんな時間!早く寝なきゃ!」と焦って子どもたちを寝かしつけていたので、全然リラックス時間は設けられていませんでした。
今は、数日に1回は「敢えてブログを書かないでのんびりする時間」を設けるようにしました。
やっぱり、精神的余裕が全然違いますね。寝付きも良くなりました。
「日記」を書き始めます皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。つい先日の過去記事でも、「少しくだけた内容で短めな文章でも、記事にしよう」と路線変更してみたのです。と書きましたが、今回から、そのライトな内容の記事を「[…]
「思考の余白」を作る方法
- ぼーっとする
- 考えを書き出す
私は時間があれば常に情報をインプットしたり(読書・スマホ)、考え事をしてしまうので、この「思考の余白」を作るのが一番苦手です…。
ぼーっとする
「ぼーっとすることは時間の無駄」と考える人は多いと思います。
しかし、最近の脳科学研究では、その重要性が証明されています。
特に何の作業もしていない「ぼーっとした状態」「ぼんやりした状態」の時、脳内では「デフォルトモード・ネットワーク」が活発に稼働しているのです。
デフォルトモード・ネットワークは、いうなれば「脳のスタンバイ状態」です。
このスタンバイ状態において、これからの自分の身に起こり得ることをシミュレーションしたり、
自分の過去の経験や記憶を整理・統合したり、今の自分が置かれている状況を分析したりと、
いろいろなイメージや記憶を想起させながら、脳内で「自分のこれからをよりよいものにしていくための準備」を整えているのです。
人間の脳ってすごいですね…!
デフォルトモード・ネットワークが稼働する時間が少ないと、前頭前野の物事を深く考える機能が低下します。
結果として、注意力、集中力、思考力、判断力、記憶力、ひらめきなどの想像力などがすべて低下し、脳の老化も進みやすくなるのです。
私もインプットし過ぎ・考え過ぎでかなり脳が疲労してしまうので、最近はぼーっとする時間を「今から10分!」などと決めて意識的に設けるようにしています。
考えを書き出す
皆さん、「人間の脳は同時に3つのことしか処理できない」という説をご存知ですか?
つまり、脳の中にはトレイが3つあって、そこに情報が入ってきて、それを処理してはまた次の情報を処理していく…というイメージです。
空のトレイがあるほど、脳は余裕を持って仕事ができ、効率よく仕事がこなせます。
空のトレイがなくなると、脳は余裕がなくなるので、作業効率が著しく低下してしまいます。
そうならないように、「考えは全て書き出して、脳のトレイをどんどん空にするべき」です。
私も実践していますが、この効果は絶大ですよ!
私は何でもメモするクセがあるので、「書き出さないと思考がぐちゃぐちゃして気持ち悪い」とすら思います。
どんどん空にすることで、どんどん情報が入ってくる…つまり「休まらない」ということのないように気をつけなければいけませんが…(笑)。
夫に仕事の悩みを相談してみた皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。私は、いつもは「人の相談にのる側」の人間です。職場では、専属産業医として社員さんの相談にのりまくり、家庭では、同時に話しかけてくる夫・子どもたちの[…]
「心の余白」を作る方法
- ヨガ
- 笑う
心が狭くなっていると、些細なことに感情的に反応してしまいます。
夫や子どもにイライラしてしまうことがあっても、「夫も子どもも悪くない。それは心が狭くなっている自分のせい」だと思うようにしています。
周囲に迷惑をかけないためにも、もちろん自分自身のためにも、「心の余白」を作らないといけませんね。
ヨガ
私の趣味のひとつに、ヨガがあります。
育児で心身ともにガタガタになっていた時、ボディビルをやっている社員さんにオススメされまして。
職場の朝礼で導入したのですが、ヨガをすると劇的に身体が軽くなり精神も安定するのです。
本当に生まれ変わったように清々しい気持ちになります。
皆さんの中にも心身の不調を感じている方がいらっしゃったら、是非やってみていただきたいです!
まずはYouTubeで、無料で体験してみてはいかがでしょうか。
私のオススメのYouTubeチャンネルは『B-life』です!
たくさん動画がありますので、自分の悩みに合ったものを気の向くままに選んでください。
ヨガの効果は、科学的にも証明されています。
アメリカの研究では、ヨガを週に1-2回2年間行った女性は、そうでない女性に比べて、ストレスのある出来事からの回復が早いことが報告されています。
運動することがストレスに良い理由として、ストレスで受けたダメージを運動で覆せる(具体的にいうと、脳の細胞を守りながら感情を安定させる働きを生み出す)ためや、
気持ちが良いと感じるホルモン(エンドルフィン)によりストレスに対応できる力がつくためと言われています。
皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。2022年もあとわずかですね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍で激務に耐えている方もいることでしょう。本当にお疲れ様です。この年末年始、皆様に少しでも心安らぐ時間がありま[…]
笑う
最近、意識して笑顔を作るようにしています。
というのも、最近加齢により「頬が下がって、表情が乏しくなったな…」と感じていたため、
表情筋トレーニングを始めたのです(まさかの美容目的 笑)。
しかし、「笑う」ことの効果は、表情が豊かになるだけではありません。
「笑う」効果に関して、カリフォルニア大学が興味深い研究を発表しています。
被検者の心拍数、体温、肌の電気信号、筋肉の緊張などを測定しながら、笑顔、恐怖、怒りの表情をしてもらいます。
すると、「笑顔」をつくるとわずか10秒で、「安心」しているのと同様の身体的な変化があらわれました。
笑顔の効果には、このように即効性があるのです。
脳科学的にいうと、笑顔をつくるとセロトニン、ドーパミン、エンドルフィンという3つの脳内物質が出ます。
これらの物質が出ると、ストレスホルモンが下がり、副交感神経が優位になります。
つまり、笑顔には緊張を緩和してストレスを解消する作用があるのです。
また、笑顔でいる人は、30年後の幸福度が高いとのこと。
未来の自分のためにも、今から笑顔をつくっていきましょう!
老いに悩んでいた私の救世主、MEGUMIさん皆さんこんにちは、更紗(さらさ)です。私ももう30代後半になりまして…老いを自覚するようになりました。いつまでも若いつもりでいましたが、産後は自分の衰えが無視出来ない程に目立っ[…]
人生の余白
ギャップイヤー
最後に、「人生の余白」についてです。
皆さんは「ギャップイヤー」という制度をご存知ですか?
大学の入学試験に合格した学生が、高校卒業後に一定の休学期間を得てから入学する制度。英国で始まった。
[補説]休学中の行動は自由で、ボランティア活動や留学、旅行などで見聞を広めたりするなどの例が多い。大学卒業後から大学院進学前・就職前までの期間に適用されることもある。 (デジタル大辞典)
日本では、このような空白期間が就職面でマイナスに作用する慣習が根強いため、ほぼ普及していないのですが、私は素晴らしい制度だと思います。
私は、このギャップイヤーのような人生の寄り道の期間を「人生の余白」と呼ぶことにします。
皆さんも、「一生このまま、ほぼ休みなく医師として働き続ける」のではなく、「敢えて休職して、別の活動をしてみる」期間があってもいいのではないでしょうか。
私は過去に医療ボランティアにも参加したことがありますが、「一年だけ」など期間限定でボランティアに来ている方たちがいました。
もちろん、医師とは全く関係のない活動でもいいと思います。
皆さんも、「人生の余白」を楽しんでみませんか?
海外移住にチャンレンジ!
私にとっては、2024年の海外移住がそれにあたります。
(私は寄り道とは思っていなくて、こっちを本道にしたいのですが、まだどうなるか分かりませんので…)
「日本でこれまで通り医師として働き続ける」のでしたら、大抵のことは予測できますが、
「海外でフルリモートワークをする」というのは全く未知の世界です。
もちろん様々な困難が待ち受けていると思いますが、それでもいいので私はその世界に飛び込んでみます。
人生100年時代、そういうチャレンジする期間があってもいいですよね。
『更紗の医師転職ブログ』にようこそ。こんにちは、管理人の更紗(さらさ)と申します。このブログでは、働き方に悩む臨床医を対象に、より良い働き方を考えるのに役立つ情報を提供しています。何故、わざわざそんなことをしているの[…]
まとめ
ご紹介してきたように、私は下記のような「余白のある暮らし」を意識して生活しています。
- 空間の余白
- 時間の余白
- 思考の余白
- 心の余白
- 人生の余白
「余白のある暮らし」を実践してから、自分の心身が整えられ、動悸も治まってきたことを実感しています。
(もちろん、治まらない時には医療機関を受診するのでご心配なく…)
もし、皆さんの生活に取り入れられそうなことがありましたら、是非お試しください。
では、また!